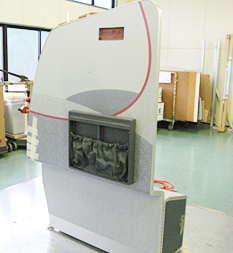宮崎県へ進出を決めた理由
なぜ宮崎に製造拠点を作ったかというと、20年前にボーイング747などの航空機の需要が2倍、3倍に膨れ上がっていて、内装するギャレーやラバトリーの生産がとても追いつかない状況が続いていました。そこで、既に宮崎には技術を持った整備拠点がありましたので、とにかく生産量を増やすために宮崎でも生産をすることになったのが始まりです。しかしながら、整備拠点が宮崎にあったからという言うよりも、整備拠点があったことによって宮崎をよく知っていて、宮崎の良さを十分に分かっていたということが、生産拠点を設けた大きな理由ですね。
創業時には、田野町(現宮崎市)をはじめ地域の方々に大変お世話になりましたし、県も含め様々な優遇制度で、いろいろと御支援をいただけました。立地をした後も、何かと世話を焼いてくれて、行政を身近に感じていますね。
ここは、宮崎空港、宮崎港、インターチェンジが近く、交通アクセスの面で大変恵まれています。製品の出荷では、陸送や航空便、船便を活用していますが、利便性は高いです。県外の方は宮崎の物流の不便さを懸念されている方がいらっしゃいますが、少なくとも我々はここで物流面の不便さをさほど感じたことはありません。
進出してよかったと思うこと
発足して20年ですから、平均年齢は34歳と大変若いのが特徴です。 発足当初から、宮崎で採用した人材を積極的に東京や海外のグループに出して、トレーニングを積んでもらいました。人間は経験と環境を与えれば、何でもできるようになるんですね。何と言っても、宮崎の方は勤勉で素直、誠実ですから、どんどん吸収して伸びてくれます。このように人材育成に力を入れて、宮崎ジャムコも段々と力を付けてきました。 社員は3人を除いて全て現地採用で対応していて、設立当初に採用した方は今では会社を支える人材にまで育ってくれました。 これからは、設計にも力を入れていきたいと考えており、設計から調達、加工、組立まで一貫体制の構築を目指していきます。
宮崎は環境が大変素晴らしいところです。宮崎ジャムコの周辺も穏やかな天候で、緑に恵まれ、とても静かなところにあって、人柄もよい。まさに、モノづくりを行うに当たって豊かな環境が揃っていますね。
東日本大震災の影響について
仙台空港にある仙台整備工場が多大な被害を受けましたが、様々な方面からの支援があり、2011年10月より営業を再開しました。 また、我々の製品に使用する部品の一部が東北地方で製造しているものもあり、その部品の調達が困難になり納品に間に合わないという不安を抱えた時期もありましたが、なんとかその時期も乗り越えることができました。 本当に皆さまのご支援のおかげだと思います。本当にありがとうございました。
今後の展開と可能性
宮崎ジャムコの今後の展開として、設計部門の強化を図っていきたいと考えています。現在設計部門には22名在籍していますが、来年は、東京から4名連れてきまして、地元から4名採用し、計8名ほど増員を図り、エンジニアリングを強化する予定です。 これまで設計部門に関しては、立川市(東京都)や新潟県の工場に依っていた部分もありました。しかしながら、開発から製造、納品までの一連の過程を宮崎ジャムコで完結していく、つまり、全部自分たちでやっていく、自立することが重要になってきました。 宮崎ジャムコ内で製造過程を完結できる能力を持つことは、今回の東日本大震災のような想定外の災害が起こった場合にも企業活動の機能停止のリスクを回避できるといった、リスクヘッジの観点からも重要なことだと思いますし、ジャムコグループ全体の能力向上にも繋がると思います。
宮崎について
私自身、寒いのが苦手でして、風邪引きやすいですし、肩は凝りますし。その点、宮崎県は暖かいですね。 そのほか、アクティビティとしては、釣りやゴルフなどありますが、果物狩りも楽しめますよね。私は小林市にあるリンゴ農園に2回ほど行きました。宮崎は海も山も市街地から近く、自然豊かで本当に良い所ですね。 私の出身地はここから100kmくらい離れたところの鹿児島県肝付町という所です。もともと農家だったということもあり、時間があれば宮崎で土地を借りて野菜を栽培しています。そうすると気分転換に非常にいいですね。去年、今年は雨が多くて収穫が少なかったですが、自然相手ですからしょうがないですね。
進出を検討している企業へのメッセージ
宮崎ジャムコの発展だけでなく、地場企業及び関連会社との共存共栄への対応ということに力を入れております。できるだけ、宮崎単独の技術力による生産体制を構築していくため、地場企業や進出を検討されている企業の皆様と共に連携していきたいと考えております。